月一夜
…月明かりの中に浮かび上がっている、うっすらと色づいた肌が目に眩しくて、仕方が無かった。
(ああもう……おまえ、珊瑚。なんでこんなに無防備なんだ…)
あどけない表情に浮かぶ安らいだ表情に魅入って、そっと頬に口付ける。
床に広がった黒髪を梳くと、それは耳障りのよい音をたてて、ゆっくりと滑り落ちて行った。
浸るくらいに呑ませた酒のせいで、体温が随分上がっているのだろう。
それで存分に温まった黒絹の手触りはしっとりと滑らかで――…いやでも衣の下の手触りを思い出さずにはいられなかった。
静かな寝息を立てる新妻の様子を静かに見下ろして、自分の浅ましさを自覚する…なんて、随分となかったことだ。
それはたぶん、珊瑚が何時もこちらに譲歩して合わせてくれている部分が多いからだ。
縋ればそれを忘れてしまえるくらいに、求めればそれ以上のものを必ず返してくれていたから、自覚しないですんでいたのだ。
それだけの心を砕いてくれているのだと、それが分からないほど愚かではないつもりだ。
つまり…
(すまん、無理をさせているな)
夫婦としてはあって当然の営みでさえ、本当はまだまだ苦痛であるはずだ。
そしてそれは自分にとっては欠かすことができなくとも、
珊瑚にとってはれほど大切ではないということも知っていた。
彼女は甘くて優しい抱擁が好きなのであって、それ以上は別段無くても良いものだからだ。
柔らかく腕に抱いて、髪を梳いて…口付けの一つでも施せばそれで十分、満たされて満足してしまうからだ。
それ以上を「もっと」「欲しい」と強請られたことなんか一度だってない事実を、弥勒はきちんと把握していた。
それを初心で無垢だからと納得出来たうちは良かった。
募らせていたのは苛立ちではなどでは決してなく、紛れも無い優しさで…許してやれたうちはまだ待っていてやれる余裕があった。
けれどもこんな風に酒が入ってしまうと――…最近はどうにも自制が利かなくなる瞬間がある。
自分の欲望がなによりも優先されてしまう瞬間。
特にこんな…月光の中に浮かぶ白い肌が、うっすらと紅色に染まる様を目にしたりしたらもうダメだ。
触れたい、味わいたい、貪りつくしたい――…
そんな欲望があとからあとから湧き出してきて、歯止めが利かなくなってしまう。
まして珊瑚は今、無防備極まりない寝顔を晒して夢の中を漂っている最中で、
こんな風にじっとりした視線や募っていく情欲を止めることなんか、気づくことさえ不可能なのだ。
始めてしまえば否応なしに起きだすに決まっている。
けれどもどちらかといえば致すに至る過程、触れるまでの一瞬が一番緊張を強いられるのだ。…自分も、珊瑚も。
特に珊瑚は未だに熱っぽい視線を向けると…それだけで萎縮して竦む。
何時だって怖がらせないように丁寧にしているつもりでも、される側に回ることなんか不可能で、
その痛みも何も本当のところ自分は知ることは出来ない。
しかも夢中になるあまり最中にどんな無理を強いているものか記憶が飛ぶこともしばしば。
情けないが、新妻がいったい何を怖がっているのかを真実理解することなんか出来はしないのだ。
まあ十中八九、半ば引き摺るようにして強引に振り回していることが原因なのだろうが…。
とん、と床置いた杯の中で、今宵の月がゆったりと嘲笑っている。
波打つそこに、情欲に塗れ、熱病にでも罹ったかのように熱っぽい目をした男が映っている。
ここに居るのは清廉な法師などではない。
目の前で寝入っている女の夫なのだと言い聞かされた気がして、促された今更な自覚に思わず笑いが浮かんでくるようだった。
――…だったら迷うことなんか一つもないだろ?
喉から手が出るほど欲しい供物は、目の前に在る。
何時ものように口説いて、とろとろになるまで蕩けさせて押し倒す…なんて手間を掛けるまでもなく、しどけない姿を晒して。
すとん、と心に落ちた声は誰の声だったのか、こんなに酩酊してるような状態では考えている余裕などない。
虚ろに彷徨う目がふっと傍らに逸れて、女の綺麗な肌に釘付けになって…
寝込みを襲うほど飢えてるのかと、僅かに残った自制の心と、欲望に率直な心が、絶妙な均衡を保って揺れていた。
踏み込むか、踏み止まるか…それでもその振り子の先が、大きく傾く瞬間はついに訪れる。
「ん…ぅ……法師さま…ぁ…」
寝返りを打った珊瑚の腕が、くったりと自分の腕をとらえ、絡みつき、抱きしめてきたのだ。
気持ちよく夢の中を彷徨っている心地だった。
それが一変して、身体の内側から何かが蕩けだすような…じわりとした疼きを自覚させられて覚醒を促された。
うっすらと眸を瞬かせて、結ばない輪郭の中に最初に飛び込んできたのは、夫である弥勒の眼差しだ。
じっとりと熱っぽい眸と――…熱い手指。
輪郭を結ぶのを待つまでも無くハッ意識が鮮明になったのは、触れる先から起こる刺激を明瞭に感じ取ったからだ。
「や…なに?…法師さま」
「なにって…この状況見てそういうこというか?おまえ」
くす、とした愉悦が肌の上を滑り落ち、深みのある艶声が耳朶を擽って…
それで珊瑚は、本当の意味で目が覚めたように感じていた。
何をされているのかを理解したと同時に、込み上げて来たのは猛烈な羞恥だった。
下に敷いていたのがとっくに剥ぎ取られていたらしい小袖だと知れて、カッと全身が紅に染まっていく。
圧し掛かるようだった夫の胸を押し返して、開かされていた膝を閉じようと躍起になる。
――…でも。
「止める理由なんか無いだろうが」
「だってこんな…卑怯じゃないか、人が寝てる隙に、なんて…」
つまりはそれに尽きる。
しかも好き勝手にあちこちを触りまくるなんてこと、誰だって許せるはずが無いだろう。
まして、
「おまえが素直にさせてくれないのが悪い」
…こんな風に開き直られたら、許せるものだって許せなくなってしまうのに。
ムッとして更に押し返す手をやんわりと掴み取られ、口付けを落とされて、床に留め置かれる。
宥めるように髪を梳かれ、曝け出された胸元にも口付けが降りてきて…名を呼ばれる。
…強引に迫られている時でも、どうしてか弥勒の口付けは基本的にはとても優しい。
それを知っているから、珊瑚は何時だって最後はちゃんと受け入れてきた。
だから…普段であったなら抵抗もここまでの話で、諦めて好きにさせてしまっていただろう。
でも今日は、悪足掻きと分かってはいても抵抗する手を緩める気にはどうしてもなれなかった。
それだけ怒りも羞恥も、普段の何倍も強く珊瑚を縛っていたからだ。
「や…っ、やだって、言ってるだろ…!触らないで…」
…いつもだったら。
こんな風に断固として拒めば絶対に手を引いてくれる自信が珊瑚にはあった。
弥勒という男が、こういう繋がりを自分がまだまだ怖がっていることをちゃんと知ってくれていたからだ。
でも、
「だったら好きなだけ抵抗していたらいいだろう。…止める気なんかありませんけどね、全く」
…思わず耳を疑った。
無理にはしない、それが夫である彼の矜持だと思っていた。
それくらい何時だってこちらを気遣ってくれているのを知っていた。
これまで一度だって、己の欲望を優先させて推し進めるなんてこと、されたことはなかったのに。
それだけに、今日のこの凶行の理由が知れなくて、
珊瑚はひやりとした恐れを抱いて、瞠る眸で怜悧な美貌を見遣った。
熱で浮かされた切れ長の双眸に宿るのは、紛れも無い自分への情欲に違いない。
それが分かってしまったから、珊瑚は胸に添えた手はそのままに、一度も攻める言葉を放つことは出来なかった。
魅入って、魅入られる。
触れて、感じて、想いの深さを思い知る。
それを一度でも痛感してしまっている身で、こんな目で見詰められたら最後だった。
肌の感触を確かめるように何度も何度も弛む乳房を弄ばれても、赤く熟れた其処を舌で嬲られても…
どうしてももう、「なぜ」ということはおろか、「やめて」ということさえ出来なかった。
「珊瑚…」
誘うように名を呼ばれて、柔らかく腕に抱き込まれる。
耳朶に注ぎ込まれた「愛してる」の言葉は切り札といっていい。
その声で、甘く切なく訴えかけられたら、どれだけ頑ななものも柔らかく解れて蕩けてしまいそうになるのだ。
弥勒が確信犯であることは間違いなくても、それをかわせるだけの術を珊瑚はまだ会得していない。
結局出来ることといえば、ただただくったりと身を委ねることくらいなのだ。
だから、
(しょうがないなあ、もう…)
そんな気持ちになって、今日もまたその首に腕を絡ませ、
声が掠れても、震えても…
降りてきた薄い唇に自らの口唇を重ねて、精一杯を強請るのだ。
「い…一回。だけ、だよ…約束、破ったらもう絶対させて上げないから…」
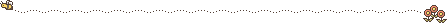
月華氷人の満都さまより頂きました。
裏ものをリクエストいたしまして、私の好みに合わせて書いて下さった一品でございます。
大変おいしくいただきました。
満都さん、本当にありがとうございました!
改めまして、これからもよろしくお願いいたします。
Alles liebe,
漆間 周