Hydrangea Beat
雫は雲より滴りて、地上に弾ける。
雨粒を跳ね返す木々の葉は生命の源への歓喜を。
紫陽花にたたえられた水滴は丸みを帯び、したたり落ちて行く。
一層美しくなった紫と共に。
Hydrangea Beat
梅雨がやって来た。
毎日のどんよりとした空には嫌気がさす。
ぬかるむ道は泥を跳ね返し、草履がすぐに痛む。
「ああもう、毎日毎日雨で鬱陶しいくらいだよ」
笠をくいと持ち上げ珊瑚は暗澹たる灰色の空を見上げた。
雨だれはおさまることを知らない。
「全くですなあ」
弥勒は珊瑚にならって空を見上げた。
小さな笠は頭を濡らさずとも遠慮なく衣を濡らしていく。
「かごめさまのものを借りてくればよかったですね」
彼女の笠は柄がついており、不思議な素材で出来た布が雨をはじく。
足元は濡れるものの、衣服への被害はあまりない。
近くに妖気を感じたものだから、二人は今その調査に出かけている。
村外れの森はもうすぐだ。
森の中へ入れば木々がすこしはこの雨を防いでくれるだろう。
「しかしまあ……なんとも。弱い妖気ですな」
「ほんと。これ意味あるのかな」
まあ然程気にならなかったからこそ、犬夜叉は二人に任せたのだが。
「法師さま、多分これこの森の奥だと思う」
一本のけもの道をたどりながら、珊瑚は妖気のする方向を指さした。
「ええ、私も感じております」
ま、行きますか。
弱い、と感じたから珊瑚も戦闘服には着替えてはいない。
雲母も連れず、飛来骨と暗器のみだ。
なぜならさして害をなすようなものには感じられなかったから。
二人はただ歩いて行く。
無言である。
笠を抱えて、雨の代わりに霧立ち込めるけもの道をひたすらたどる。
じんわりと滲む汗。
湿気が半端ではないのだ。
しかもそれでいて、肌寒い。
「珊瑚、大丈夫ですか?」
つう、とこめかみからつたい落ちた汗に気付いて、弥勒は声をかけた。
小袖一枚では寒かろうと思い、己の袈裟を解いて彼女にかけてやる。
「あ……大丈夫だよ。法師さまが寒くなっちゃうだろ?」
「おなごが体を冷やすものではありません」
「分かったけど……」
戸惑いがちにその紫の衣を肩にかけ前で結ぶ。
「ていうかこれいつもどうやって着てるのさ」
いまいち着方が分からず、ただ羽織るようにした彼女が呟いた。
「ああ、それ、まあ布一枚ですから。ちょっと体に巻いて結べばいいだけですよ」
ふぅん、と返して珊瑚はきゅと袈裟を握り締める。
確かに、少しは暖かい。
「あ、でも法師さまみたいに着たいってわけじゃないからね」
「いえ……それはあまり。まず丈が長いでしょうし……珊瑚が尼になっては私は手を出せませんからなあ」
などと答えて、弥勒はいつもの如く、あの場所に手を伸ばそうとした。
が、気付かれたらしく、腕ははたかれてしまった。
「尼になったら、って法師さまだって法師のくせして女に手出してるからあんまり関係ないんじゃないの?」
何してんのよ、とねめつける彼女に乾いた笑いしか返せない。
「はは、また痛いところを」
「破戒法師」
「おっしゃる通りでございます」
はあ、とため息ついて弥勒は念を込め錫杖をしゃらん、と鳴らした。
霧が晴れて行く。
「着いたね」
「分かっておりましたか」
「ナメてもらっちゃ困るよ」
ふっ、と戦う女の顔で笑うと、彼女は獲物にくいと力をこめた。
が、その力はすぐに緩められた。
「法師さま、これ……」
そこにあったのは紫陽花が見事に咲き誇る清らかな泉。
妖気の源は確かにここではあったが、妖の仕業とは思えぬ美しさである。
「ほう……これはまた」
ところどころに淡い緑の葉をのぞかせ、一面に紫の芳香を漂わせている。
その空間は、明らかに森からは切り離されていた。
なぜなら、空が丸い。
そして晴れているにも関わらず、雨の雫がしたたり落ちている。
――遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん、遊ぶ子供の声きけば、我が身さえこそ動がるれ。
舞え舞え蝸牛、舞はぬものならば、馬の子や牛の子に蹴させてん、踏破せてん、真に美しく舞うたらば、華の園まで遊ばせん。
東屋の妻とも終に成らざりけるもの故に、何とてむねを合せ初めけむ。
「うた、ごえ……?」
――ああこひはせんのやいばのごとし わがむねつらぬきてはなさず
あまだれ 紫陽花に こぼれ 届かぬや いとしきひとに
なみだかれても やまぬや 陪蘆
か細い声が木霊するように響く。
見上げる空は丸い。
澄んだ空なのに、狐の嫁入りの如く、雨は止まない。
「どうやら……恋に捕らわれたおなごの心が妖となって留まっているようですね」
「…………」
珊瑚は答えない。
「珊瑚?」
聞いてます、珊瑚?
返事がないので彼女を見れば呆然と澄んだ空を見上げる彼女の姿があった。
目には精気がない。
ただぼんやりと、空を見つめている。
紫の香が立ち上る。
やがて彼女はぱたりと獲物を落とし、雨だれに合わせるように、舞い始めた。
――しまった……!
弥勒は妖怪の本体を滅するべく泉を見渡す。
だがいくら感覚を研ぎ澄ませても見つからない。
珊瑚に目をやれば、彼女は弥勒と目を合わすこともせず、舞い続けている。
身のこなしは美しい。
鍛え抜かれたからだのしなやかさがいっそうそれを引き立てている。
そして、結の解けた黒髪が、雨に合わせおどるように揺れる。
艶やかに、雫は彼女の黒髪を伝って行く。
舞う表情は恋に憑かれたおなごの如く、はるか極楽を見るような恍惚をたたえている。
だが、どこかしらそこにその終わりを見るかのような哀愁が漂う瞬間がある。
――美しい。
ただ一言に尽きた。それ以上の言葉は要らなかった。
妖を探ることも忘れ、紫陽花の中で舞い続ける彼女から目が離せない。
「そこな、法師どの」
突如、背後からの声に弥勒はやっと我を取り戻した。
「これは……お前の仕業か?」
しゃらん。
突きつける錫杖の先には。
儚げに十二単衣を着た女の姿。
ぬばたまの黒髪は、地につくほど長く、切れ長の瞳はどこか別の世界を見つめている。
女は、嗤った。
「恋を、していらっしゃる」
す、と手を伸ばし開けるのは舞扇。
――はるははな……
京乃四季を口ずさみながら、く、と笠に見たて額に構えた舞扇の下で、妖はふふふ、と笑う。
「あの娘の願いを叶えれば、解放して差し上げましょうぞ」
「……願い?」
「わらわは恋に破れしもの。恋に囚われしもの。この泉に幾年おるかは分かりませぬ」
ぱちん。
舞扇が閉じられ、今度はそれが弥勒に向けられる。
「この東と同じ想いをかの娘はしておる。救ってやれ」
「おな、じ……?」
――なみだかれても やまぬや 陪蘆
弥勒はそれにはっ、と気付く。
東と名乗った妖はふふ、と笑んだ。
「分かったようだな、では行け。さらばじゃ」
声を残して妖は消えた。
だが未だ珊瑚は舞を続けている。
――うずめの舞い、か……?
どこかそれに似た動作を見つけて、弥勒はふと考える。
天の岩宿を開けようとしている?
ならば?
それはどういう意味だ?
なぜ天照は岩宿にこもった?
うずめの舞いは何を意味している?
――そうか!
一瞬のひらめきに、弥勒は珊瑚にかけより、舞う彼女の手を取り、そっと耳元に口をよせ、囁いた。
「…………が、消えた」
瞬間、珊瑚の体は力を失い、くたりと彼に倒れかかる。
同時に咲き誇った紫陽花は次々と霞のように消えていく。
ただそこには、どんよりとした灰色の空が見渡せる、森の中の泉があるだけだった。
***
――千の刃、か。
帰路、意識を失った彼女をおぶりながら弥勒は一人考える。
そんなもの、つらぬかれているのはこちらの方だ。
しかし――。
珊瑚の、舞いの意味は。
弥勒は己の右手をきゅ、と握りしめた。
自嘲めいた笑みがこぼれる。
雨は降り止まない。
自分も珊瑚も、ずぶ濡れだ。
泥まみれの己の草履を見やって弥勒は願った。
天の岩宿が、いつか必ず、開くことを。
fin.
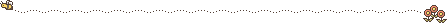
まず、イメージは坂本龍一のTHOUSAND KNIVESから。
ただ情景が書きたくて書いた感じもあります。
オリジナル妖怪は初めてですね。
中の長唄などは梁塵秘抄と、自分で書いたものとです。
まず、雨がリズミカルに降り注ぐ紫陽花のイメージから始まったのですが、紫陽花の花言葉が「非情」ということで、こういう流れに持って行きました。
色々注釈が必要そうなので(文章内で気付かせる力がないのです:苦笑)
「涙が枯れても陪蘆(雅楽の曲)は止まない」というのは、どんなに悲しくても世の中は陽気である、という意味をこめました。
これが法師の気持ちになっております。
そしてうずめの舞いは天の岩宿に悲しみのあまりこもった天照を楽しませ、そこから出そうとする舞いです。
と、いうことで法師が何を言ったかはお分かりいただけましたでしょうか?
ちなみに今回html変換ソフトを始めて使用しました。
改行タグを打つ手間が減って楽でした、ほんと。
ではでは、ここまで読んでくださってありがとうございました。
2009.06.07 漆間 周