不器用なわたしたち≪直視できない≫
例えば、雲母の背中に跨っている時に鼻腔をくすぐる彼女の香。
戦う時にするどくすがめられるその切れ長の瞳。
その小袖の後でくくった髪が左右に揺れる様。
そして、時たま見せる無垢な笑顔。
弥勒は沈もうとしている下弦の月を見て瞠目した。
一人の時間というのは、いかにも自分らしい、と思う。
こういつもいつも鉄面皮でいると、自分の性というのがどこに行ってしまったのかと戸惑う時すらある。
それでも切り替えることは決して忘れない。
悟られてはならない。
己の孤独を、心中を。
それは仏の道に生きるものとしても、妖怪と戦う身としても、何より風穴という宿命を背負った自分に一番必要なことだ。
同情などいらない。
同情するなら――金をくれ。
いや、いっそこの立場をお前が代われ。
それでも生きなければいけないから、大切な仲間が出来てしまったから、後に戻れない。
たまに見せてしまいそうになる弱みに、自分はひるむ。
心を許していいのか、悪いのか。
去りゆくのは本人の勝手だ。
それがサダメというなら受け入れる。
けれど残されたものは、どうなるという?
だから、他人に深く入ることは許されない。
それでも、犬夜叉たちといるとぐらりと歪むように傾ぐ己の感情に歯止めが効かない。
珊瑚といると、他の女性以上に何かを感じてしまう。
――それこそ愛だと。
分かっているから、認めることが出来ない。
彼女が自分に向ける、密かでそれでいてひたむきな恋心も知っているから、余計に認めることが出来ない。
認めたくない。
昼間の彼女の笑顔を思い出して、まるで平穏な生活に身を置く人間のように唇をうっすらと笑みに変えてしまって、はっとする。
すぐにぎゅっと引き締めて今見える光景を両の目に刻みこむ。
風が吹き抜けて。
何もかも連れ去るように。
雲が流れて、どこかへ消える、月を隠す。
闇より濃い闇が迫る。
誰も知らない己がそこに立っている。
今を見ると、過去さえも見えてくる。
孤独に旅した昼間の太陽に、父上と叫んだあの日の轟音。
―― !
そう叫んでしまいたい。
もし、願が叶うならば、彼女の腕に抱かれて、赤子のように泣き叫びたい。
「んなもん……出来るわけがねえ」
一瞬の願望に目を背けて、自嘲の笑みを浮かべた。
音もなく立ち上がる。
自分が法師で良かったと思う。
この黒衣は、闇夜によく馴染むから。
fin.
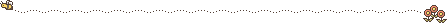
以前上げました≪分からない≫の弥勒編でございます。
会話全くなし。弥勒サマ独り言。
空白の部分は、空白にしたかったので空白にいたしました。
時々使う、卑怯なテクです。西尾維新先生や奈須きのこ先生がよく使用されるような。
しかしセカイ系が苦手なものだから、避けてるのですがね;
時系列はいつだろう、結構二人の仲が進展しているけれど、でも踏み切れない、そんな時でしょうか。
次の連作は弥珊として書きたいと思っております。
それでは、ここまで読んで下さってありがとうございました。
2009.08.29 漆間 周