マブイの困惑
ぐいと伸びる腕がある。
雲母が後ろを振り返った時には、手甲につつまれた手のひらが目の前にあって、目の前は真っ暗だった。
ぐいと尻尾がつかまれる。
「雲母、お前やってくれましたね」
何のこと、とでも言うように、雲母が首を傾げるのを弥勒がにやりと笑って見つめる。
「自分の姿ですけれど、あまり気分の良いものではありませんでした」
尻尾を掴んだまま、すたすたと文字通りの速さで移動する。
向かう先は骨喰いの井戸。
「しかしお前ねえ」
井戸に腰かけた弥勒が雲母の真っ赤な瞳を見つめた。
二つの尾が揺れる。
「結局、珊瑚に伝えたかったことは言えたのですか?」
ふぅ、とため息して、彼がしゃらんと錫杖を鳴らすと、雲母は嬉しそうに弥勒の膝に飛び乗った。
「言えたと?」
みっ、と鳴いてから腹をみせてごろごろと喉を鳴らす雲母に弥勒の頬は思わずゆるんだ。
そうか、と呟いて腹を撫でてやる。
心地よさそうにみぃみぃと鳴く雲母は純粋に可愛らしい。
これだけ可愛らしいのに、戦闘ともなれば自分と珊瑚を乗せて危険な場所も躊躇することなく飛び込んでいく。
頼もしい相方であるとつくづく思うから、珊瑚とこの猫又の間柄が時々気になる時がある。
雲母の性別は知らないし、それは異性への嫉妬ではない。
幼い時分を知っている、時分の知らない過去を知ることが、自分には到底届かない場所だから気になるし、妬きもするのだ。
「お前が私と話を出来ると良いのだが」
手をとめた弥勒にくるりと器用に雲母は身を返す。
ぱっと猫又が向かった先には見知った影。
「おや、珊瑚」
「雲母、あれから法師さまと仲良くなったみたいだね?」
肩に乗った相棒の顎をくすぐって珊瑚が微笑む。
「……仲良くなったのか、何なのか」
むくれた弥勒に珊瑚が近づいてきて、目の前に立つ。
「何かあったの?」
「いえ、別に」
簡単に返答して、雲母と珊瑚を交互に見やる。
別にと言えば深追いされる時もあるが、されない時もある。
今の場合は後者だ。
理由は様々だが、大体の雰囲気で分かる。
「そっか。てっきり焼きもちでもやいてるのかと思ったよ」
「は?」
意外そうに顔を上げた弥勒の頬を、珊瑚がつんとつついた。
「図星って顔してるけど」
「……は、はあ。そうですか」
「何を妬いてるわけ? 雲母と私とどっちが、とか?」
「違いますよ」
全く図星のようでずれていた。
頬杖をついて珊瑚の肩の上にいる雲母をじいと見る。
何、と見つめ返す眼。
またふぅ、とため息をついて、立ち上がる。
しゃらんと錫杖が鳴る。
「お前の幼い時分を私は知らないから」
顔を向けられなかったのは、こう言うことを言う時にどんな顔をすれば良いのか分からないから。
どんな顔をしているのか分からないのに、その顔を見られるのは嫌だった。
「あたしだって法師さまの昔のことは知らないけど?」
振り返れば、眉根を寄せてわがままを言う子供のような顔の珊瑚がいた。
自分もそんな表情で先ほどの科白を言ったのかもしれないと思った。
「それは、そうだ」
「法師さまが……昔どれだけ悪行非道をしてたかとかもね」
気付けば横からぐいと顔をのぞきこまれて、ぷいと目を反らした。
「ばか」
「……お前こそ」
とんと触れた肩が自然と笑いを誘う。
「お前に似ているとは思いたくなかったが、案外似ているかもな」
「あたしは法師さまなんかには絶対似てないから」
「な、お前、それはどういう……」
伸ばしかけた腕は自然と引き止められる。
法師さま子供みたいなんだから、と笑って、ねえ雲母と囁いて、走り去る珊瑚の後ろ姿を見送る。
――子供みたい、か?
その言葉に存外ぐさりとやられてしまったようで、弥勒は頭を抱えた。
「全く……私は案外初だというわけか?」
答えなど当然なく、それでも自覚が迫る。
夜のことなら、一夜限りの女なら、慣れてもこういうことには慣れていない。
「……お前だって、初なくせに」
悔し紛れに、呟いた。
fin.
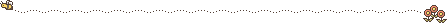
乙女弥勒。タイトルから、マブイのいたずらの後日ということにしております。
弥勒法師は寝ることには慣れていても恋には慣れていないと思うので、そんな彼を書いてみました。
それでは、ここまで読んで下さってありがとうございました。
2009.09.20 漆間 周