もう歌しかきこえない
「おい、お前ら、朝だぞ」
頭上からの犬夜叉の声に弥勒と珊瑚は顔を上げた。
光は見えぬが、体は刻限を覚えている。
音と風の気配が朝だと教えてくれた。
ゆえに起きてはいたが……この暗闇の中では本当に朝なのか、それが不安で。
昨晩から二人はただ手を繋いだままだった。
「準備は出来ているんですか?」
「おう、もう行くつもりだが……」
「大丈夫なの? まだここにいた方が……それか近くの村で宿をとるのが一番なんじゃあ」
心配そうなかごめの声が聞こえる。
今二人が感じるのは視覚以外の全て。
頼りになるのは仲間がいること。
「そうだね……もし妖怪に出食わしても、あたしたち戦えないし」
「けっ、俺が一人で片付けるっつーの」
「でももし相手が沢山だったらどうするのです? 私もこの見えない状況では風穴が使えない」
弥勒の言葉に犬夜叉がふーむ、とうなる。
「かごめさま、近くに村はあるのですか? ならば宿をとりましょう。私はその方が賢明かと思いますので」
「ああ、あたしも出来たらそうしてもらいたい……ごめんね、へましたばっかりに」
ちち、という朝の鳥の鳴き声に心地良く吹き抜ける風。
それは感じるが、折角の朝の光が見えない。
どこまでも続く暗闇。
感じるのは、互いの手の体温。
「いいのよ、気にしなくったって。でもその状態いつまで続くのかしら……」
「ええ、気になってはいるのです。あの鳥の妖怪が最期に仕掛けた呪詛なら何か方法があるはずなのですが」
弥勒はく、と己の右手の数珠を辿る。
「ああ、仕留めたはずなんだ。二匹いたのを片方があたし、もう片方を法師さまが退治した」
「鳥の妖怪ねえ……」
「……待て。お前ら、仕留めてねえぞ」
しばらく考えた様子だった彼が言葉を発する。
「何だって!?」
――そうだ、確かに仕留めたはず。だってあの時、舞い落ちる妖怪の黒い翼に、あたしの飛来骨が命中した証に血が。
「そんなはずは。視界を奪われる直前に妖の血を見ました。私の方は霧散していった」
珊瑚の心を読んだかのような発言に、珊瑚がえ、と彼のいるであろう方向を向く。
「はは、なんとなく言いたいことが分かりまして」
くすり、と微かな笑い声が聞こえた。
「違う。あの時、まだ匂いがしてた。俺はお前らが追っ払っただけにしたんだと勘違いしてたんだ」
「ならばまだあの二対の妖怪は生きていると?」
「だろうな。まあ、動けない程度にはなってるんだろうが」
弥勒と珊瑚は顔を見合せた。
見えなくなって何時間だろうか、何となく感覚がつかめるのだ。
相手がどこにいるか、何をしているかが。
恐らく失敗したことに唇を噛みしめているであろう彼女に弥勒は言う。
「気にすることはない、それならばあれを本当に退治してしまえば良いことだ」
「でも」
「私の方も失敗している。何かが、おかしい」
犬夜叉に顔を向け、尋ねる弥勒。
「ああ。で、お前ら二対、って言ったな? 俺には一匹の臭いしかしてなかった」
「何!?」
「弥勒さまと珊瑚ちゃんには二匹の妖怪が見えていて……でも犬夜叉は一匹だって言う。ってことは……」
「一匹の妖怪が作った幻覚かの?」
「七宝、見えないのをいいことにそんなに近くで顔を覗き込むな、気配で分かるんだ」
「すまん、弥勒」
「雲母……ありがと」
すり寄ってくる二匹の小さな仲間に二人は笑う。
「ま、とりあえず今日の宿をお願いいたします。我々のせいで手間取らせてしまって申し訳ない」
「んなもん仕方ねえこったろうが。とっとと行くぜ」
恐らく村の方向に踵を返した犬夜叉。
その気配を汲みとって、二人も腰を上げる。
「二人とも……大丈夫なの?」
気遣わしげなかごめの声。
二人笑って返す。
「大丈夫、気配とかは分かる。音も聞こえるしさ」
「ええ」
「そっか。んと……で、いつまで二人手繋いでるの?」
「え!?」
かごめの言葉に慌てて珊瑚は繋いでいた右手を払う。
くすくすとかごめが笑う。
「いいじゃない、別に」
「そうですよ、良いではありませんか」
「よ、良くないの! 別に……一人だって歩けるんだから!」
そして珊瑚は一人犬夜叉の気配を追って歩き出す。
「あーあ、意地張っちゃって」
見送るかごめの声に弥勒はくすりと笑って、自分も犬夜叉の気配を追って歩き始めた。
「あ、ちょっと待ってよ弥勒さま!」
雲母は珊瑚の肩に、七宝は弥勒の肩にそれぞれいる状況で、自分が置いていかれるなんて。
あーあ、とため息をついて自転車を引っ張り、仲間の後を追う。
――でも。見えないのに気配だけで歩けるなんてやっぱり人間離れしてるわ。
二人の強さを改めて痛感したかごめだった。
ざあ、と風が森の方からなびく。
嫌な気配を感じ取ってかごめは目をひそめた。
だが、それほど特定できる妖気を感じない。
――ちゃんと退治して、二人を元に戻さなくっちゃ!
決意を秘めてかごめは歩く。
だって、好きな人の顔が見えないなんて、哀しいじゃない。
***
宿の中。
おめえらうろちょろすると危ねえからじっとしてろ、という犬夜叉の一言に部屋で弥勒と珊瑚はかごめと共に待機していたのだが。
犬夜叉は、調べてくる、と言って森の方に向かった。
「犬夜叉のやつ、口では何だかんだ言っておっても心配しとるようじゃの」
「そうねえ」
ふふ、とかごめは笑う。
「しかし、こうしているのも暇なことこの上ないのですが……」
深いため息が弥勒の口から漏れる。
「まーた弥勒さま、村の女の子ひっかけに行きたいとかでしょ」
「そうなの、え? え?」
隣の珊瑚からの冷たい気配に弥勒はがっくりと頭を垂れた。
「違います。折角こう、はねを伸ばす時間が出来たというのに外にも出られないのは」
「だから一人でどこに行くってのさ」
「一人じゃありません、お前と、です」
二人の会話にかごめは自然と笑みを浮かべた。
何だかんだで彼らは昨晩から身を寄せ合うばかり。
視界のない不安ゆえにそうなるのだろうか。
だが、まるで見えなくても見えているような二人の様子に心底その絆を感じる。
「……分かったけどさ。でも、この状況じゃ歩けないし」
む、と頬を染めて俯いた珊瑚の様子に、かごめはぱちんと手を叩く。
「な、何? かごめちゃん」
「いいこと思いついたの」
えへ、と笑って彼女は雲母を指さす。
もっとも珊瑚には見えていないのだが。
「雲母に道案内してもらってけばいいのよ。それに、もし小さな妖怪に出食わしても雲母なら大丈夫でしょ?」
「ほーぅ、それはそれは。確かに名案ですな。では、そういたしますか、珊瑚」
「え、あ、う、うん……」
弥勒に手を引かれて立ち上がる。
雲母のみっ、と鳴く声が聞こえて、二人はそれについて歩く。
「七宝ちゃん、あの二人、いい雰囲気じゃない?」
「そうじゃのう」
「聞こえてますよ、かごめさま」
「あ、ははは……」
小声で言ったつもりだったのだが、今の状況のせいで彼らは聴覚が鋭敏になっているらしい。
ありがとうございます、といった様子の頬笑みを彼女の方に向けて――微妙にずれてはいたが、彼は宿を後にした。
***
「で、どこに行くって言うのさ」
「さあ? 雲母、どこか良いところ、ありますか?」
弥勒はかがんで猫又に話しかける。
外の陽ざしの温かさを感じる。
それだけで幸福な気がして、珊瑚は弥勒が外に連れ出してくれたことをありがたく思った。
「み」
「付いてこいって」
「雲母の言うこと、分かるんですね」
「ああ、ずっと一緒にいるんだから当たり前だろ」
「なら、行きますか」
そしてそっと重ねられる彼の左手。
は、と珊瑚はそれを振り払う。
「い、いい……! 一人で、その、歩けるから!」
触れた瞬間に高鳴った鼓動。
それが聞こえないように彼から思わず遠ざかる。
そして一人、歩いて行く。
後から彼が付いてくる気配がある。
雲母がついたよ、とでも言うかのように鳴いた。
――が。
「う、っわ!」
雲母に付いて歩いたはずだったが、思わぬところで足をすべらせ、恐らく河原なのだろう、落ちてしまう。
「全く、だから手をつなごうと言ったのに……って、ああ!?」
珊瑚に駆け寄ろうとして、同じところでつまづき滑り落ちる弥勒。
その様に珊瑚が思わず噴き出す。
「何言ってんの、あんたまで……く、あははは、あははは、もうっ……ふふ、ふふふ」
「な、何もそんなに笑わなくとも良いではありませんか」
弥勒の苦笑になお珊瑚の笑いは止まらない。
つられて弥勒も笑いだす。
二人、姿勢を元に戻して河原に座る。
ゆっくりと、珊瑚は目を閉じた。
開けていても閉じていても、見えるものは同じなのだが。
弥勒の肩に頭を乗せる。
優しい、抹香の香。
ふわり、と風が凪いで、水の香まで感じるような気がした。
せせらぎの音は優しい。
暗闇の中で、自分を取り巻く世界が、少しだけ見えた気がした。
中でも鮮明に、愛しいその人の姿は浮かぶ。
きっと、彼も瞠目している。
「ねえ」
「何です?」
「昨晩……犬夜叉の迎え待ってる時、法師さま、見えなくとも見えるものがある、って言ったでしょ。あたしが見える、って。今ちょっとだけ、分かる気がする」
「そうか」
嬉しそうに、微笑む気配。
そして、手甲のはめられた右手が、ゆっくりと頭を撫でた。
「すまないな。私がもっと注意していれば、こんなことにはならなかったかもしれん」
「……そんなことないよ。あたしだって注意足らずだったんだ。妖怪の正体も見破れなかったんだし」
ふ、と全身の力を抜くと、まるで予期していたかのように弥勒は珊瑚を抱きとめる。
「法師さま……」
優しく回された腕が。
その衣の香が。
自分を、全身を包んで。
まるでそこだけ、切り取られた世界のように。
「ねえ、こっち向いて」
「はい?」
く、と向けられた彼の輪郭をそっと撫でて唇の場所を探す。
なぞる指は彼の存在を確かめる。
「珊瑚、何を……ん」
紡ごうとした言葉は、女の唇で止められた。
――悪く、ない。
弥勒は目を閉じて、ただ彼女の唇を受け止める。
自分からは何もしない。
今、彼女が必要としているものが何か分かる気がしたから。
やがて離れたそれに、弥勒は言葉をかける。
「大丈夫、きちんと元に戻る」
「うん……」
「弥勒、珊瑚ー!」
「あ、犬夜叉」
「いいところを邪魔しに来る奴だ……」
「何か言った?」
とん、と二人の前に犬夜叉が着地する。
「ちょっと森で調べてきた。どうも例の妖怪は夜になると動くらしい。夜になったら俺たちが退治しに行く。だからお前らは宿で待ってろ。で、もう帰るぞ」
一気に告げられた言葉に珊瑚が反論する。
「犬夜叉。退治……あたしに、やらせて」
「はぁ!? お前、正気か!?」
「私も、自分の手でやらせていただきたいものですな」
「み、弥勒、お前まで……。馬鹿か。おめえら自分が目え見えねえの分かってんのかよ!?」
困惑したような、怒ったような、犬夜叉の声。
「分かっておりますよ。だがこの決着、我々につけさせてほしい」
「ぐ……」
犬夜叉の沈黙。
しばしの間を置いて、呆れたような声が返ってきた。
「わーったよ、てめえらでやれ。場所までは雲母で行け。夜になったら教えてやる」
「ふ、物わかりが良くなったな、犬夜叉」
「てめえとじゃ口で勝てねえんだよ! ったく……馬鹿も休み休み言いやがれ」
つい、とそっぽを向いたであろう彼に珊瑚がぼそりと呟く。
「馬鹿に馬鹿って言われたくないよね……」
「おいこら珊瑚、何か言ったか」
「何も」
「けっ」
おら、帰るぞ。
その一言に、雲母が変化し、二人を乗せて宿へ向かう。
「何だ、雲母、こうするなら来る時もこうしてくれればよかったのに」
ふふ、と雲母の頭を撫でながら珊瑚は言う。
「分かってませんな。雲母なりの気遣いというやつです」
「はぁ?」
「……もう、いいです」
そして帰った宿で二人は犬夜叉から妖怪の詳細を聞きだし、夜に備えた。
後編へ
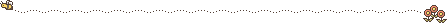
前後編の予定を中編も加えました。
後編は妖怪退治に切り替えたかったので。
それでは、ここまで読んで下さってありがとうございました。
2009.07.19 漆間 周